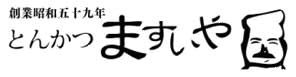
四十年かけて辿り着いた食への追求は美味しいだけじゃダメなんだ!


ここにしかないここでしか出会えない「味」
ますいやはそれぞれの目的にあった食の楽しみ方をご提案いたします。気の会う人と好きな食べ物を楽しみながら食べるその裏側には栄養という大切な体のバランスを整えてくれる食の要がある!少しでもお客様のお役に立てるますいやを目指しています。
こだわり抜いた食材で作るので、どれも自信を持ってお出しできるメニューです。
とんかつはもちろん、焼き物や一品料理にいたるまで試行錯誤を繰り返しながら厳選した逸品となっております。
「今日はこれにしよう」
「次来たらこれを食べてみよう」
何度も訪れたくなる美味しく楽しいメニューをご用意しております。





